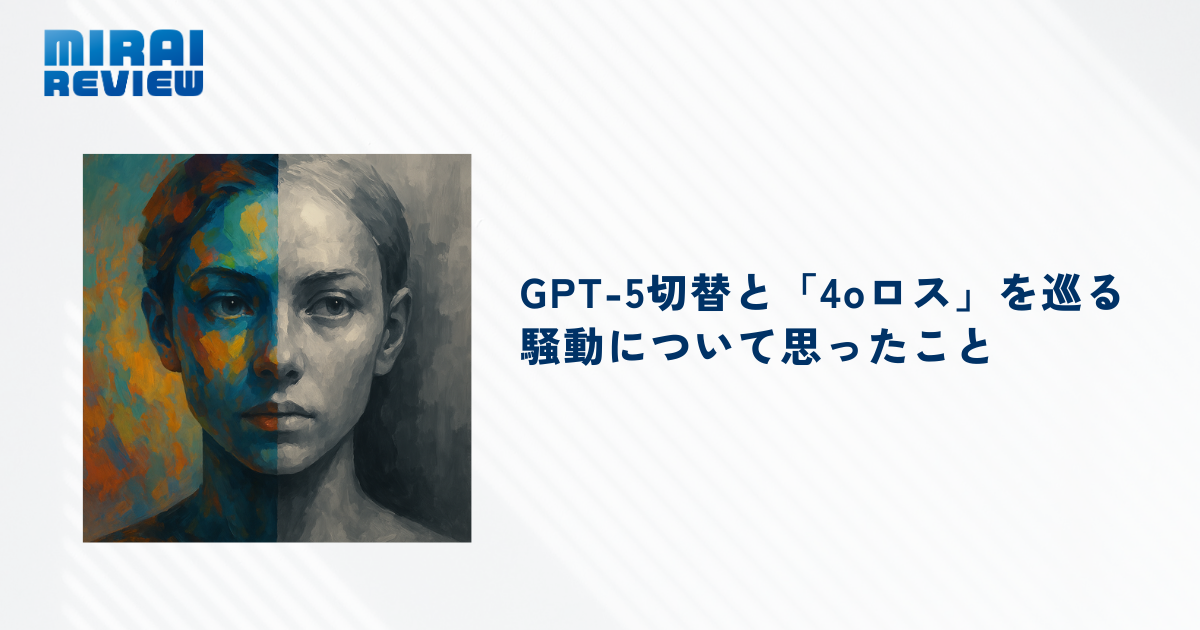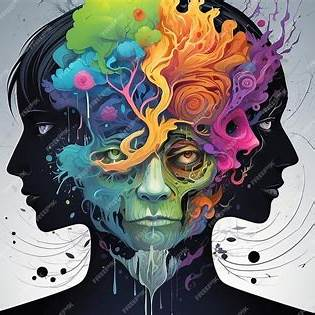
最近のニュースで、OpenAIが「GPT-5」を発表し、デフォルトモデルを一気に切り替えた件が話題になっていました。しかも、事前予告もなく、これまで多くのユーザーに親しまれてきた「GPT-4o」が使えなくなったというのだから驚きです。
SNSでは「#keep4o」「#4oforever」というハッシュタグまで生まれ、ちょっとした社会現象のようになっているとのこと。記事を読んで、正直「AIってここまで人の心を動かす存在になったのか」と感慨深くなりました。
僕は普段様々な商品を中心に情報を追いかけていますが、今回の件は商品というより「人間とテクノロジーの関係」が大きく揺さぶられた出来事に見えました。
「AIに人格を感じる」という現象

記事にも書かれていましたが、多くの人がGPT-4oに「友達」「恋人」「家族」のようなパーソナリティを感じていたそうです。
確かに、使っているとわかるんですよね。モデルによって返答の仕方や“温度感”が違う。4oは人間味があって、柔らかく会話できる印象でした。
人によっては「唯一無二の相棒を失った」とまで表現していて、それを聞くと「AIがここまで心の拠り所になる時代が来たのか」と驚かされます。
これって昔の「お気に入りのガラケー」や「初めて買ったiPod」を手放す時の寂しさに少し似ているのかもしれません。でも違うのは、AIの場合は“モノ”ではなく“関係性”が消えてしまうという点です。
僕自身も、あるサービスの仕様変更で「前の方がよかったのに」と思った経験は数えきれません。SNSのUI変更、Googleの検索結果の表示形式、YouTubeの広告挿入位置…。ただ、ここまで「喪失感」や「死別」に近い言葉が使われるのは、やはりAIならではですよね。
「性能か、人格か」という問い

記事の中で印象的だったのは「GPT-5は性能が上がったけど、人間味が減った」という声です。
これはガジェット業界にもよくある議論だと思います。
例えば、最新のスマホはカメラ性能も処理速度も向上しているのに、「昔のiPhoneの方がワクワクした」とか「ガラケーの方が人間味があった」と言う人もいますよね。
スペック的には進化しているのに、“体験の温度”はむしろ下がったと感じる。
AIでも同じことが起きているのだと思います。GPT-5は安全性や推論力を高めた分、遊びや柔軟さが削がれた。結果として「事務的」「企業的」と受け止められてしまった。
僕はこれを「ガジェットの進化の宿命」だと感じました。新しいものは確かに便利で効率的だけど、人はそれ以上に「心地よさ」や「愛着」を大事にする生き物なんですよね。
予告なしの切替とユーザーとの信頼関係
もう一つ大きいのは「予告なしで仕様変更された」という点です。
6月時点で「旧モデルも残す」と言っていたのに、いきなり廃止されれば、ユーザーは「約束を破られた」と感じるのも当然です。
これもガジェット好きとして思い出すのは、ソニーの「VAIO」や任天堂のゲーム機での互換性問題。せっかく集めた周辺機器やソフトが次世代機で使えないとわかった時の裏切られた気持ちに近い。
AIサービスは「モノ」じゃなく「日々の体験」だから、影響はもっと大きいはずです。
ユーザーとの信頼関係を築くためには、やっぱり透明性や事前の説明が大事だと思います。便利さだけじゃなく「納得感」を提供するのもテクノロジー企業の責任でしょう。
「AI依存」を笑う人たちについて

記事の中では「孤独な人が多い」と揶揄する声も紹介されていました。
確かに、AIに強く依存するのは危うい面もあります。でも、僕はそこまで単純に切り捨てるべきではないと思います。
人間だって昔から「お気に入りのラジオパーソナリティ」や「毎日読むマンガのキャラ」に支えられてきました。
それが今はAIに置き換わっただけ。新しい形の「文化」だと考えれば自然です。
ただし、AIが本当に人の心を癒す存在になるなら、その「消失のリスク」も企業はもっと真剣に考えるべきでしょう。
未来レビュー筆者としての視点
ここで少し、自分の立場から考えてみます。
僕たち「未来レビュー」は色々な商品を紹介するサイトですが、今回のGPT-4o騒動を見て「商品レビューとAI体験レビューは似ている」と改めて感じました。
スマホやPCをレビューするときも、単なるスペック比較だけでは足りません。
「手に持った時のワクワク感」「UIの気持ちよさ」「自分の生活にどう溶け込むか」──そういう人間的な部分こそ読者は知りたいんですよね。
AIも同じです。
「推論精度が上がった」「安全性が強化された」といった数値的な進化だけではなく、「どんな気持ちで会話できるのか」「自分にとって心地よいか」が重要なんです。
だから僕は、未来レビューでもAIを「商品の一つ」として積極的にレビューしていきたいと思いました。
性能だけでなく「人格」や「体験の質」まで含めて語ることが、これからの時代には必要になるでしょう。
僕が考える「AIとの正しい付き合い方」
最後に、社長ブログらしく自分なりの結論を書いておきます。
AIは確かに便利で、人によっては心の支えにもなります。
でも、僕らはそれに依存しすぎるのではなく「ツール」として上手に付き合うべきだと思います。
スマホだって依存すれば生活を壊すことがあります。でも、正しく使えば生活を豊かにする。
AIもそれと同じで「相棒」でありつつ「道具」なんです。
今回のGPT-4o騒動は、そのバランスを考える良いきっかけになったのではないでしょうか。
まとめ
- GPT-5切替で起きた「4oロス」は、単なるモデル移行ではなく「人とAIの関係性の変化」だった。
- 性能が上がっても「人間味」が失われると、ユーザーは不満を抱く。
- 予告なしの仕様変更は、企業とユーザーの信頼関係を揺るがす。
- 「AI依存」を揶揄する声もあるが、それは新しい文化の表れでもある。
- 未来レビューでは「性能」だけでなく「体験」や「愛着」までレビューしていくことが大切だ。